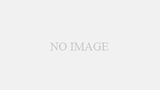〈テレビ局に“隠し撮り”されて抗議が殺到したことも…恐山の僧侶が明かした「テレビ取材のトラウマ」〉から続く
「ヤクザ上がりなのか!?」「あんなヤツ、昔は一人もいなかった!」と電話で抗議を受けたことも……。恐山菩提寺で副住職を務める南直哉さんが「テレビ出演から遠ざかる」ようになった「ある事件」とは? 最新刊『苦しくて切ないすべての人たちへ』(新潮社)より一部抜粋してお届けする。(全2回の2回目/前編を読む)
【写真ページ】「元ヤクザ」に間違えられた住職の顔を見る(写真多数)

恐山の禅僧で、著作も多くある南直哉さん。彼がテレビ出演から遠ざかるようになった「ある事件」とは? ©新潮社
テレビのトラウマ
当時私は、「暫到和尚」(入門志願の新人修行僧)の教育係に配属されていた。私の係は、暫到和尚の所持品検査や基本的作法などを指導する部署で、私に言わせると「それなりに」厳格であった(後日当時の暫到和尚に会うと、私の「それなりに」は、彼らの「とんでもなく」になる)。
この部署の撮影は前日に終わり、私が指導当番のその日は、「いつものとおりでよし!」と、係の責任者にわざわざ確認の上、私は「いつものとおり」仕事をしたのである。
ところが、その日、私が所持品検査をした新人僧1人が、あろうことか、どこかの「クラブ」(女性とお酒を飲むところ)のメンバーズカードを持ったまま来てしまったのである!
所持品検査から1年ほど経ったあと、「どうして途中で捨てなかったんだ?」と彼に尋ねると、
「気がついたんですが、あまりのことに焦りと困惑で頭が真っ白になって、足だけ機械のように動いて、気がついたら門まで着いちゃったんです」(恐るべきは永平寺の圧力!)
入門の前晩、「娑婆との別れ」に当たり、友人たちが盛大な「壮行会」を開いてくれたらしく、彼はしたたか酔って、カードをもらったことも、どういう事情で持って来てしまったのかも、皆目わからなかったそうである。
しかし、あの時カードを見つけた私には、そんな事情は関係ない。「なんだ! これはっ!!」の一喝とともに、文字通り首根っこを押さえて、玄関から外に叩き出したら、その新人僧は階段から転げ落ちた。三、四段の短い階段だったが、どういうわけか、彼は両手両足をひろげて一回転するような、派手な落ち方で、まさにこのシーンを隠し撮りされたのである。
さらに「見どころ」は続く。
「いったいどういうつもりで永平寺に来たんだ!」と、立ち上がりかけた新人僧に、上から大声で怒鳴ったら、その私の背後右から、建設会社の課長を退職して入門した小柄な同輩が、「ここはなあ、ススキノやカブキチョウじゃねえんだぞっ!」。
この番組を見た大抵の人は、このセリフも私が言ったと信じているが、誓って私ではない。私はほぼ下戸で、「ススキノ」は全く知らず、「カブキチョウ」も新宿の怖いところ、くらいの認識しかなかった。
テレビのせいで全国の僧侶たちから抗議殺到
後に聞いたら、番組のこのシーンが流れると、当時の永平寺の全外線電話が鳴り響き、全国の曹洞宗住職や僧侶の人たちから、怒声さながらの抗議が延々と続いたという。
「何だ、あの背の高い若僧は!?」
「ヤクザ上がりなのか!?」
「本山でカブキチョウとは何だ!!」
「あんなヤツ、昔は一人もいなかった!」
翌朝は大変だった。永平寺にテレビは無いから、何が起こったか知る由もない。一夜明けたら、先輩から、
「直哉! お前、下山だ!」
「どうするつもりだ? アレ」
老師方から、
「直哉和尚、困ったのお……」
「もう少し、やりようがのお……」
それまで師匠と親しか知らなかった私の出家が親戚中にバレて、実家の電話も一晩中鳴り続けたという。
「何がどうしたの!?」
「出家、なんで許したの!?」
当時の永平寺にまともな広報担当者がいなかったので、この映像を含め、ほとんど無制限に撮影して、そのまま放送できたのである。
その後数年して、マスコミ各位にその名が知られるほど「厳格極まりない」広報担当者になった私は、知り合いの某公共放送局員に、さる筋から入手したビデオを見せて、
「これ、どこから撮ってるの?」
「少なくとも、100メートル以上は離れているでしょうねえ」
「でも、音は?」
「すごくデカい、高感度の集音マイクがあるんです」
この番組はビデオになって販売され、さらにDVD化した。以来、10年以上、永平寺入門志願者の「事前教育」ビデオの定番となった。
「こんなヤツ、さすがにもういないだろう」と思ってやって来ると、僧堂などで私を見て、「まだいる!」と驚愕する破目になったそうである。
この一件のトラウマが、私の「メディア原体験」であり、今に至るまで、「黙っていると何をされるかわからん」という警戒感と、一貫した「消極姿勢」の元になっているのだ。
テレビの語る「言葉の問題」
以来、数度、テレビに出たが、トラウマとは別に、一つ強く感じたことがある。それは、テレビで語る言葉の問題である。
テレビ番組は長くて1時間、特番でも2時間、どんなに深刻な問題でも、いかに複雑なテーマでも、その時間内にケリをつけなければならない。すると、言葉は、考えてから出すのでは遅くなりやすい。条件反射的に言葉が出ないと、往々にして間に合わないし、それが出来る者が重宝される。
ということは、テレビの中の言葉は、声が大きく、刺激的な言い回しほど、目立つし「売れる」だろう。それは往々にして、「思考のショートカット」になりかねない。私はテレビの言葉に馴れることの危険を感じたのである。
おそらく、ネット社会の拡大と深化は、この言葉の傾向を加速させるだろう。より刺激的で強い言葉が吸引力を持ち、その言葉もAIが用意することになりかねない。
自分で考える「面倒」を避け、アルゴリズムが導出した数個の選択肢を、「自分の考え」として選択するという、考えの省力化と効率化が奨励されるかもしれない。
それで何が悪い、という人もいるだろうが、私はそれに共感できない。おそらく、それは自分の言葉に対するプライドゆえであろう。そんなプライドに今後も意味があるかどうかは、定かではないが。
(南 直哉/Webオリジナル(外部転載))