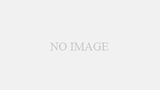一般ドライバーが自家用車を使い、客を有料で運ぶ「ライドシェア」が近く仙台市内で始まる。タクシー事業者の管理下で限定的に実施する「日本版」で、市内の9社が参入意向を示した。ライドシェアに前向きな動きにも映るが、タクシー業界の本音は「一般ドライバーが増えると需要が奪われる」。日本版にあえて手を挙げてタクシー不足を解消し、ライドシェアの「全面解禁」を阻止したい思惑が見え隠れする。(経済部・庄子鉄平)
[日本版ライドシェア] 一般ドライバーがタクシー事業者と雇用契約を結んで実施する。事業者はドライバーに研修を受けさせ、勤務状況や車両を管理する。配車は「GO」「ウーバー」といったアプリを利用。発着地と運賃を事前に確定した上で乗車し、目的地に到着後、キャッシュレス決済で支払う。使用する車両は外からライドシェアと分かるように表示する。
タクシー協会は「反対」
4月に東京などで解禁された日本版は、タクシーが足りない地域や曜日、時間帯に運行台数を限って実施する。国土交通省は4月下旬、配車アプリのデータに基づき、仙台市内は金曜午後4~7時台に50台、土曜午前0~3時台に30台が不足していると公表した。
他地域に比べると、仙台の不足数はかなり少ない。タクシーの登録台数が同規模の広島(広島市など)や埼玉県南中央(さいたま市など)は、同じ調査方法で金曜夜と土曜の不足数が220~580台に及ぶ。仙台にライドシェアが必要なのかどうか、業界内には疑問の声が少なくない。
市内は2002年の規制緩和でタクシーが急増し、06年に3003台に達して社会問題化した。その後、業界全体で減車に取り組み、2245台まで削減したが、現在も供給過剰の恐れがある「準特定地域」に指定されている。
東北運輸局の担当者も「仙台の場合は、明らかにタクシーが足りないという状況ではない」と認める。
それでも運輸局が市内のタクシー事業者に参入意向を聞いたところ、金曜に9社26台、土曜に5社21台の希望があった。運輸局は不足台数の半分を枠として各社に配分し、事業者の許可申請を経て実施する。
宮城県タクシー協会(仙台市)は、基本的にライドシェア解禁に反対の立場を取る。第2種の運転免許を持たない一般ドライバーの活用は、安全面への懸念とともに非正規雇用の拡大につながりかねないためだ。
「全面解禁」を阻止したい思惑か
最も警戒するのは海外と同様に、タクシー事業者以外も参入を認める「全面解禁」。政府はデジタル行財政改革会議で論点を整理した上で、6月中をめどに結論を出すことにしている。
協会の高沢雅哉会長は「日本版で『不足』が埋まらなければ、全面解禁の口実になってしまう。日本版も問題の多い制度だが、全面解禁だけは阻止しなければならない。これが業界の共通認識だ」と、参入希望が多かった背景を説明する。
ライドシェアは都市部や観光地のタクシー不足に対応するため、政府が一部解禁に踏み切った。コロナ禍で運転手の離職が相次ぎ、人手不足となった一方、インバウンド(訪日客)増加で移動交通の需要は高まる。
ただ、仙台市内は昨年5月のタクシー運賃引き上げと、新型コロナウイルス5類移行による需要の上向きで、運転手の収入が改善しつつあり、人手不足に解消の兆しが見られる。協会によると、毎月30~50人の運転手志望者の応募がある。
杜の都交通(仙台市)は金曜と土曜に各1台を配分され、仙台の日本版に参入する。岩崎伸副社長は「タクシー運転手は足りないので、ライドシェアで雇った人が興味を持ってくれたらうれしい。転職希望があれば2種免許取得などもフォローする」と戦略を描く。