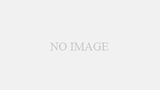若い世代は給料よりもプライベートの充実を優先する傾向が強い LUIS ALVAREZ/GETTY IMAGES
<週に5日も働くのはもう古い。これからは生産性を上げて、きっちり働いてしっかり休むのが時代の流れだ>
新型コロナウイルスの感染爆発で、私たちの働き方は劇的に変わった。職場に行かなくても仕事はできる。ズームを通じて顧客や同僚に「会う」こともできる。それが当たり前になった。でも、いま30~40代のミレニアル世代はもっと楽をしたい。もっとプライベートな時間が欲しい。だから、働くのは週に4日でいいと思っている。
20世紀には「週5勤務」が先進国の世界標準だったが、これからは働く日を1日減らし、週40時間労働から週32時間に移行する一方、仕事量は減らさず給料も(たいていのケースでは)減らさない。そういう仕組みを先駆的に、部分的にでも導入した企業はたくさんある。
SMBC GMO PAYMENT【新規店舗におすすめ】オールインワン決済端末を、1年間月額料金0円でお試し
この流れには勢いがある。自称「民主的社会主義者」のバーニー・サンダース米上院議員も「週4勤務」制の推進派だ。3月には自らが委員長を務める上院の厚生・教育・労働・年金委員会の公聴会で、こう発言している。
「悲しいことだが、ほかの豊かな先進諸国に比べて、アメリカ人はずっと長く働かされている。この事実が一般の人々の暮らしにどのような意味を持つか、この点を議論しようではないか。2022年の数字で、アメリカの労働者は勤勉で知られる日本の労働者より年間204時間も多く働いていた。イギリスの労働者より279時間、ドイツの労働者より470時間も長く働いていた」(本誌はこれらの数字について電子メールでサンダースに確認を求めたが、返信を得られていない)
政治家だけではない。今は多くの営利企業や非営利団体が、革命的な働き方改革に取り組んでいる。
働く日を減らし、ゆっくり休める日を増やせば、どんなメリットがあるか。この点を検証する試みはアメリカでもイギリスでも、EU諸国でも行われている。そしてどうやら、40代以下の若い世代はこの変化を歓迎しているようだ。
「週4勤務」で生産性が上がる
本誌の委嘱で英調査会社レッドフィールド&ウィルトン・ストラテジーズが実施した世論調査によれば、労働時間の短縮を最も強く支持しているのはミレニアル世代だ。
4月6~7日にアメリカの有権者4000人を対象に行われたこの調査では、回答者の63%が週4勤務への移行に賛成し、46%が「そうすれば労働者の生産性は上がる」と考えていた。
賛成が最も多かったのは30~40代のミレニアル世代で、回答者のほぼ4分の3(74%)が労働時間の短縮を望んでいた(具体的には週4勤務への移行に「大いに賛成」とした人が半数弱の44%で、「一般論として賛成」とした人が30%)。この世代で週4勤務への移行に反対と答えた人は8%のみだった。
関連するビデオ: 米雇用統計受け一時1ドル151円台に 2日の介入観測に鈴木財務大臣「コメントしない」 (テレ朝news)
about:blank
読み込み済み: 24.14%再生
現在の時刻 0:02
/
期間 1:14品質の設定全画面表示

米雇用統計受け一時1ドル151円台に 2日の介入観測に鈴木財務大臣「コメントしない」ミュート解除
0
一方、戦後の1964年までに生まれたベビーブーム世代や、それに先行する80代以上の人たちの価値観は違う。この年齢層で週4勤務を支持すると答えた人は2人に1人、「どちらとも言えない」がほぼ3人に1人だった。ちなみにミレニアル世代で「どちらとも言えない」は、4人に1人に満たない23%だった。
本誌は週4勤務のシステムを導入、あるいは試してみた企業に取材し、その成果や評価を聞いた。すると対象企業の過半数から、従業員のワークライフバランスに大幅な改善が認められ、過労で燃え尽きてしまう従業員の数が減り、従業員の定着率も向上したとの回答が得られた。
いい例がクラウドファンディング専門のサイト運営会社キックスターターだ。同社はコロナ禍が収まりつつあった22年、週4勤3休のシステムを導入した。
従業員の参加意識と生産性の向上は会社にとっても利益になる
「コロナ禍が最悪だった20年に、働き方というのは私たちの想像以上に柔軟なものだということに気付いた」と、同社の最高戦略責任者ジョン・リーランドは言う。「従業員の仕事と暮らしのバランスを改善することがもたらす利益は、どんなコストにも代え難い。従業員の参加意識と生産性が上がれば、会社にとっても利益になる」
20世紀以降、人々の「働き方革命」を推進してきたのは技術の進歩だ。20世紀前半の欧米に生まれた「週5勤務」制は、今の時代にはもう時代遅れだと、就業支援の非営利団体JVSを率いるリサ・カントリーマンキロスは言う。
「そもそも週5勤務制が生まれた時代背景は、今とは全く異なる。今の世界は、当時の人たちが想像もできなかったほど変化が速く、テクノロジー主導で動いている。私たちも週4勤務に移行したが、その効果は素晴らしい。生産性が上がる一方、ワークライフバランスが改善され、過労の訴えも減った。その結果、離職率はほぼ半分に下がった」
SMBC GMO PAYMENTstera packで「また来たい」と思われるお店に
しかし、大きな変化に想定外の副作用が伴うのは世の常。「業種にもよるが、同じ仕事量を少ない労働時間に詰め込めば、過労で燃え尽きる人が出る。それを防ぐには、ワークフローの見直しや作業工程の合理化が不可欠だ」と、中小企業向けの金融機関クラリファイ・キャピタルの共同創業者でCEOのマイケル・ベインズは言う。「個々の企業が自社のニーズに合わせて計画を練り、行動に移す必要がある」
緊急対応を迫られる医療など移行が困難な業種も
そもそも、週4勤務への移行が難しい業種もある。例えば医療だ。
カイロプラクティックなどに特化した医療機関フラウムセンターを経営するヘンリー・クリスによれば、24時間体制で患者へのサービス提供と緊急時の対応を迫られる医療機関は、そう簡単に週4勤務に移行できない。
「できればそうしたいが、現実には問題が多すぎる」と、クリスは言う。患者へのサービスを最優先しなければならない以上、スタッフの休業日を1日増やすためには就業時間の管理や人員の配置に関する新しい戦略が必要になるからだ。
いずれにせよ、年配の世代は今さら週4勤務への移行など望まないかもしれない。しかし、これからの職場を担うのはミレニアル世代や、それに続くZ世代の若い人たちだ。彼らのニーズに応えられない企業には、きっと誰も来てくれない。
生産性向上の方法を経営者にアドバイスする評論家のペニー・ゼンカーによれば、今は「給料よりもプライベートの充実を優先」する若者が増えている。そして「働く世代の志向が変わった以上、企業としても彼らの新しい価値観や期待に適応する必要がある。
勤務時間や勤務形態に柔軟性を持たせ、最新のテクノロジーを採り入れ、雇用者と労働者の価値観を擦り合わせ、個々のライフスタイルを尊重するべきだ」と語った。
そうすれば──とゼンカーは言う。
「週4勤務への移行は、より良いワークライフバランスを望む若い人材を引き付けるだろう。社会全体を見渡しても、出勤日を減らせば温室効果ガスの排出量を削減でき、みんなの幸福感が高まり、いい効果がどんどん波及していくはずだ」
アリス・ハイアム