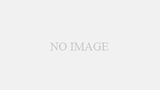仙台市は2日、世界標準のダイバーシティー(多様性)を備えたまちづくりに向け、有識者組織「ダイバーシティ推進会議」の初会合を市内で開いた。都市の包摂的成長を重視する経済協力開発機構(OECD)などの国際的な議論の潮流を念頭に置き、誰もが暮らしやすいまちの在り方を検討する。市は本年度内に4回の会合を開いて論点を集約し、来年3月下旬に指針を策定する方針。
郡市長「選ばれる都市に」
委員は国際化や福祉、男女共同参画の学識経験者、実業家ら12人で構成。郡和子市長は「選ばれる都市に成長する鍵はダイバーシティーにある。OECDの議論を踏まえながら、その考え方をまちづくり全般に折り込むことが重要だ」とあいさつした。
委員で一般財団法人ダイバーシティ研究所(大阪市)の田村太郎代表理事がダイバーシティーの概念を説明。(1)違いを受け入れる(2)互いに対等な関係を築こうとしている(3)全体として調和が取れている-状態を満たす組織や地域、取り組みを指し、持続可能性に直結すると指摘した。
「市民活動や官民連携、東日本大震災からの復興の歴史といった仙台の強みを生かしたダイバーシティーの推進を議論してほしい」との田村氏の呼びかけに対し、各委員も指針に盛り込むべき視点などについて持論を述べた。
次回は8月後半に予定。初会合を踏まえて市がまとめた指針のたたき台を基に意見を交わす。推進会議委員長に就いた東北大の大隅典子副学長は「さまざまな少数者に配慮し、共生を目指すのが私たちの方向。仙台が住みやすい市だと指針などで国内外に発信していけたらと思う」と話した。
東北大が昨年、政府の「国際卓越研究大学」の認定候補第1号に選ばれ、同大青葉山キャンパス(青葉区)にある次世代放射光施設「ナノテラス」が今年4月に本格稼働した。推進会議を設置した背景には、研究者や留学生、企業関係者を中心とする外国人の増加やジェンダー平等、障害者に配慮したまちづくりが必要との問題意識がある。