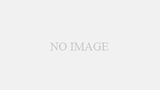24年ぶりの安値を更新する円安で、悪夢のような値上げラッシュが始まった。しかし、本当に怖いのはこれからだ。失われた30年、コロナ禍、ウクライナ危機を経て、日本を襲う新たな試練の全貌とは。
円の大暴落が止まらない。4月中旬に1ドル=126円を突破し、20年ぶりの円安水準だと大騒ぎになったが、6月13日には1ドル=135円にまで下落した。
1ドル=150円も通過点
「米国はコロナで莫大な金融緩和を行いましたが、その結果、今年5月の消費者物価指数は前年同月比で8.6%上昇と、すさまじいインフレを引き起こしました。物価を下げるために、金利を積極的に引き上げています。さらに6月からはバラまいたカネを回収し始めました」(経済評論家の藤巻健史氏)
一方、日本は日銀の黒田東彦総裁が金利をゼロ近辺にコントロールする金融緩和を維持する方針を明言している。
Photo by GettyImages
藤巻氏が続ける。
「日米の金利差が明確なのですから、海外のヘッジファンドは金利の低い円を借りて、金利の高いドルで運用する『円キャリー取引』で儲けることができる。日銀が利上げに踏み切り、かつ、おカネを回収し始めない限り、円安の流れは止まりません。1ドル=135円で、24年ぶりの円安水準だと大騒ぎしていますが、1ドル=150円でさえ、通過点にすぎません」
電気・ガス代4割増しへ
日本は資源の乏しい島国だ。ほぼすべての資源を海外から輸入している。その元手となる日本円がとてつもないスピードで暴落しているため、物価の高騰が止まらない。
とりわけ、光熱費の上昇は異常だ。平均的な家庭の場合、今年7月の電気・ガス代は合計1万4757円になる見通しだ(東京電力・東京ガスの場合)。昨年同月と比べると、3090円も値上がりしていて、実に26%の上昇率になる。
「ヨーロッパでは、すでに昨年に比べて電気・ガス代が4割上昇しています。もともと、コロナ後の経済再開で資源需要が増加したのに供給が間に合っていないことが背景にあり、そこにロシアとウクライナの戦争が拍車をかけました。
世界的な資源価格の高騰は収まる気配がなく、さらに円安が追い打ちをかけている。日本の電気・ガス代がヨーロッパのように4割増しになるのも時間の問題です」(ファイナンシャルプランナーの深野康彦氏)
光熱費だけではなく、ガソリン価格もさらに高騰していく。
「世界的に需要が拡大しているにもかかわらず、供給が増えていないため、原油高は収まる気配がありません。現在は1Lあたり約40円の補助金を出しているので、1L170円で収まっていますが、1ドル=150円になると、補助金を入れても1L200円を突破するでしょう」(経済産業研究所コンサルティングフェローの藤和彦氏)
物価高はこれからが本番
ガソリンが高くなると、運送費も高騰するため、物価の上昇が加速する。一番の被害を受けるのは、年金生活者だ。
折しも6月15日付の朝日新聞に東京都在住の78歳の主婦による悲痛な投書が掲載された。
〈物価高の中で年金は減り、店に行くのも自制しています。生鮮野菜は高騰で手が出ません。毎日の献立に悩み、同じ食材を使い回したり、そばを買う時は光熱費のことを考えて乾麺はやめたりしているほどです。(中略)
日銀の総裁や政治家の皆さんには、相次ぐ値上げが国民の死活問題になっていることを知ってほしい〉
すでに年金生活者の生活は苦しいものになっているが、庶民を直撃する物価高は、むしろこれからが本番だ。
「輸入小麦は政府が製粉会社への売り出し価格を決定していますが、今年4月に17%も引き上げました。売り出し価格は半年に一度見直され、次回は10月です。政府は10月以降も輸入小麦の価格が高騰している場合、価格を抑制すると言っていますが、その頃には参議院選挙も終わっているので、手のひらを返して値上げする可能性もある。
ガソリンの補助金も、参院選後にやめる可能性があると見ています。これらを考慮すると、秋ごろにもう一度、きつい値上げが来るかもしれません」(経済アナリストの森永康平氏)
再び「負のスパイラル」に
政府は物価高が進んでも、民間の賃金が上がれば国民の不満を和らげられると考えている節がある。たしかに一部の大企業の業績は絶好調で、給料も上がっている。
「海外に事業法人を持っている企業であれば、円安で帳簿上の利益が増えます。だからトヨタもソニーも’22年3月期決算では史上最高益になりました。春闘でも労働組合の要求に対して、満額回答で応じています」(シグマ・キャピタルのチーフ・エコノミスト・田代秀敏氏)
しかし、賃上げなど、ごく一部のグローバル企業だけ。超円安によって、国内で働く労働者の給料は上がらないどころか、むしろ下がっていく。
「大企業にとって円安はプラスの効果を持つものです。一方で、中小企業は輸入コストが上がるため、マイナスの効果があります。大きな流れとして、海外に資産を持っている企業や人はより富み、そうでない人々はいっそう生活が苦しくなっていくと考えられます」(みずほ銀行チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏)
なぜか。このメカニズムを前出の森永氏がさらに詳しく解説する。
「物価が上昇を続けていくと、どこかのタイミングで消費者が物を買うことができなくなります。そこで企業は利益を出すために、なんとか値下げをして売ろうとします。
しかし、値下げをしようにも、円安と資源高で輸入コストは変わっていません。どこで利益を出すのか。最終的に雇用者のクビを切って、利益を出すしかないわけです。正社員をリストラして、非正規雇用を増やしたり、安価で使える外国人労働者を増やしたりする。結果的に周囲に職を失った人が増えたり、もしくは自分自身が失業したりするようになり、さらに世の中の節約傾向が強まります。
消費活動が弱まり、商品がもっと売れなくなるため、企業はさらに人件費を下げるしかない。日本は再び負のスパイラルに入っていくのではないでしょうか」
超円安の先にある日本の姿とはどのようなものか。【後編】「『超円安』は日本人に何をもたらすのか」で、先行きをさらに見通す。