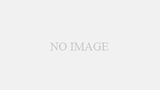東北学院大は、東日本大震災後に埋もれていた声を取り上げ、多角的に検証、発信してきた雑誌「震災学」を改称し、「被災学」第1号を発刊した。2012年に創刊され、17号を数えた「震災学」の蓄積を生かしつつ、枠組みを災害全体に広げた。
「被災学」は、他の地域で発生した地震や津波をはじめ、水害、噴火、土砂災害、豪雪なども取り上げる。編集を担当する同大地域連携センターのセンター長を務める坂本泰伸情報学部教授は「国内外での災害の多発を踏まえ、これまでの中核だった震災だけでなく、より幅広く扱う必要を感じた」と語る。
「日本は日常の中に災害があると言える。今までできていたことができなくなったり、前日までの暮らしが止まったりするのが被災だと考えている」。坂本さんは、被災をそう定義付ける。
誰がいつどこで災害に遭うかは分からない。不測の事態に備え、関連死といった災害後のダメージをどう軽減するかに編集の力点を置いた。「経験や知恵を皆で分かち合い、共に考える場にしたい。感情、データのどちらにも偏らず、多様な立場の人たちが関われる余地をつくっていく」
「被災学」の考え方を提唱したのは作家・クリエーターのいとうせいこうさん。第1号では、いとうさんへのインタビューを巻頭に掲載した。関東大震災(1923年)後、朝鮮人虐殺を引き起こした流言飛語をテーマにした、東北大災害科学国際研究所の川内淳史准教授、東北学院大国際学部の郭基煥教授の研究も、それぞれ紹介している。
元日に起きた能登半島地震にも誌面を割いた。ノンフィクションライター、臨床哲学の専門家、新聞記者の現地取材を通じて、過去にあった災害の教訓が生かされない現況、半島部や過疎地に根差す課題などを伝えた。
坂本さんは、災害後の地域像を50年、100年といった長い射程で描いていく意義を説く。そのために巻き込みたいのは10、20代。「被災から立ち直る中核となるのは若い人たち。復興への道筋を語り合う雑誌を読めば、街の未来を考えるのが面白くなるのではないか」
戦禍や感染症被害-。取り上げられるテーマは、どんどん広がっていく。坂本さんは「文系、理系問わず、さまざまな専門性が融合した雑誌体になればいい」と期待を膨らませる。
第1号はA5判、208ページ。2200円。連絡先は東北学院大地域連携課022(354)8140。
(菊地弘志)