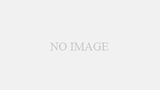若者とおっさん。世代で文化や感性が異なるのは仕方ないものの、なぜかおっさんは持論を展開したがる。その背景には、おっさん特有のルールが渦巻いているのだ。
◆すべてが“前時代的”!? おっさん式ビジネス規則
「残業を押し付けてきた上司が、その後『もう遅いから飲みにいこう』と誘ってきたのが理解できませんでした。えっ、もう遅いなら帰らせてくれるんじゃないの!?」(♂・28歳・輸入)
こうしたおっさん的ビジネスルールは、他の世代には違和感を抱かれがちだ。ただ、このようなケースは、労いとチームワーク構築のつもりで誘っているのかもと若者も一定の理解を示す。しかし、非合理的なルールには、シビアな視線を向ける。
「仕事は体で覚えろって、本当にみんな、それだけで覚えたんですか?」(♂・27歳・営業)
「店長(40代)がタイ人スタッフに『見て覚えろ』と言っててさすがにむちゃだろと思った」(♀・24歳・飲食)
同様に、技術は教えないのに「下積みは長いほどいい」というおっさんルールの非合理性もNG。
「基礎を長年やらされても、応用の機会がなきゃ変わらないのになぜなのか」(♂・25歳・IT)
「一つの職場に3年はいないとモノにならない」については「もう終身雇用はないんだし、向いていない仕事をやり続けるのは若いコには機会損失だと思う。おっさんは若いコをしばくのが育成だと勘違いしているし、若いコもドMだと『いい経験になりました』というし、見てられない」(♂・36歳・事務)という。これは若者側の意識改革も必要そうだ。
一方、テクノロジーに慣れないがゆえのおっさんルールはどうか。
「重要な要件はメールより電話」といういまだ根強いメールだけで済ますことへの不信感については、「それぞれ一長一短があるのに、電話にだけ重きをおくのがおっさんの証拠」(♀・31歳・事務)と手厳しいが、ここは「おっさんゆえに仕方ないか」という理解の声も。
ただ、ついてこれないのを変な理屈をつけて正当化するおっさんルールについては手厳しい。
「最新の物を使用して効率的に仕事をするのは、手抜きと同じ」などは、その最たる例で、「おじさんが辛うじて扱えるのはグーグルドライブ。スキッチやセンドエニウェアを提案すると、ムッとされてしまう」(♂・28歳・営業)と評判が悪いようだ。
体育会系至上主義も、若者には奇異に映る。
「聞いてもないのに『俺は体育会系だから』と言う。つまり『今後、仕事を雑に振っても不思議に思うな』という暗黙の圧力ですよね」(♂・33歳・人材派遣)
一番アウトなのは、ここ最近とみに厳しくなったセクハラ的な考え方だ。
「権力者と近しい女性は高確率で愛人だ」というセクハラ的思い込みは、もっとも「なし」とされる。
「知り合いの著名人が主催する国際イベントのお手伝いをしたのですが、客のおっさんが『君は一体何なの?』て。『スタッフです』というと、軽蔑のこもった目で『そんなことしてお金もらってんの?』と。つまり、お前は主催者の愛人だろうと。そんなおっさんは日本人だけでしたよ」(♀・34歳・自営業)
国の労働環境を左右するだけに、おっさん的ビジネスルールの是正は割と重要事項かもしれない。
<ナシな謎ルール>
・一つの職場に3年いないとモノにならない
⇒おっさんの言い分:「一通りのことを覚えるのが大体3年だから」
・重要な用件はメールより電話
⇒おっさんの言い分:「重要なことは肉声で伝えないと信頼が築けない」
・仕事は体育会系でなければならない
⇒おっさんの言い分:「仕事は元気よくハキハキとこなすもんだ」
・長時間働くほど業績が高まる
⇒おっさんの言い分:「費やした時間と努力は無駄にならない気がするから」
・長時間労働の後に飲みに誘うことはチームワークを高める
⇒おっさんの言い分:「飲んで本音で話し合うことで団結力が養われるんだよ」
・仕事は見て覚えるものだ
⇒おっさんの言い分:「仕事は失敗と試行錯誤の末に身につくものでしょ?」
・下積みは長ければ長いほどいい
⇒おっさんの言い分:「基礎を知らないヤツがデカい仕事なんてできないよ」
・最新のものを使用して効率的に仕事をするのは、手抜きと同じである
⇒おっさんの言い分:「なんでもかんでも効率化してたら真心が込もらなくなる」
・経費はどこからか出てなんとかなる
⇒おっさんの言い分:「俺たちはただ結果を出すために集中していればいい」
・権力者に仕えている女性は高確率で愛人である
⇒おっさんの言い分:「愛人の一人くらい囲えないと出世できないよね~」
★社会学者・田中俊之氏評
「今の40代以上の男性は、全体主義的文化で育った。『我が町』、『我が高校』など基本的な行動単位が『我々』であり、さらに付け加えるとPC世代なので、ケータイ文化により、行動様式が個人単位となった今の若者には、抵抗があるでしょう」
【田中俊之氏】
社会学者。大正大学心理社会学部准教授。男が男であるがゆえの悩みについて研究する男性学の第一人者。著書に『男が働かない、いいじゃないか!』(講談社+α新書)