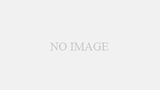ゆるくてもダメ、ブラックはもちろんダメな時代には、どのようなマネジメントが必要なのか。このたび、経営コンサルタントとして200社以上の経営者・マネジャーを支援した実績を持つ横山信弘氏が、部下を成長させつつ、良好な関係を保つ「ちょうどよいマネジメント」を解説した『若者に辞められると困るので、強く言えません:マネジャーの心の負担を減らす11のルール』を上梓した。
本記事では、管理職になることを拒む会社員が増加している背景について解説する。
出世を望まない人たちはどれぐらいいるのか?
「課長になるぐらいなら、私は会社を辞めます」
「え? どうして?」
出世するぐらいなら辞めると言いだす30代の社員がいた。とても優秀な社員だった。私どもの支援先で幹部候補と注目されていただけに、上司や役員たちは心底落胆した。
ここ数年、出世したくない会社員が激増している。私が社会に出た頃(バブル全盛期)は、誰もが「24時間働けますか?」を合言葉に出世争いを繰り広げていた。なのに、なぜこんなことになったのか?
組織として望ましいのは健全な競争があることだ。なのに「出世競争」など、まるで死語のようになってしまった。めっきり聞かなくなった。冒頭に記した「出世するぐらいなら辞める」と言いだした社員は、年収が1.3倍になると言われていた。にもかかわらず、
「課長になるぐらいなら競合他社に転職する」
と言いだした。このような話を私はここ数年、いろいろな企業の経営者から聞いている。この傾向は各種調査結果からも、明らかだろう。
2022年10月に実施された調査(ビズヒッツ)で、管理職になりたくない理由として最も多く挙げられたのが「責任が重い」というもの。男女とも傾向は似ている。「仕事・残業が増える」「割に合わないと感じる」「残業代が出ない」「人間関係で悩みそう」といった理由が上位に並んだ。
つまり、まとめると「割に合わない」ということだ。出世すると負担が増える。負担が増える割には給料も増えないし、やりがいも減る。それなら今のままのほうがいい、という考え方だ。昇進を打診されたら「断る」と答えた人は60%以上に達し、「条件次第では引き受ける」の18.8%を大きく上回っている。衝撃的としか言いようがない。
若手社員、新入社員においてはさらに顕著だ。公益財団法人日本生産性本部の「新入社員働くことの意識調査結果」では、新入社員の多くが「役職に就きたくない」と回答した。ただ若者に「割に合わない」という意識は少ない。それよりも「会社に縛られたくない」という思いが強いようだ。「専門技術を磨きたい」「組織に縛られず人脈を広げたい」といったポジティブな傾向も見られる。出世すると会社の意向に従う必要があり、自分のキャリア形成においてマイナスと捉える人が多いのかもしれない。
出世したくない3つの「本当の理由」
前述したとおり「割に合わない」ことが、出世を断る大きな理由のようだ。それにしても、なぜそのように「割に合わない」と受け止めてしまうのだろうか。多くの人と意見交換してきて、私は次の3つが「本当の理由」だと考えている。
(1)管理者の役割がよくわからない
(2)若手を育てるのに苦労する
(3)不確実性の高い時代に目標達成できない
1つひとつ解説していこう。
(1)管理者の役割がよくわからない
そもそも管理者(以下マネジャーで統一)の役割についての理解が不足していることが一番の原因だと私は考えている。多くの企業では、マネジャーの定義が曖昧だ。具体的な職務内容が明確にされていないことが多い。私が「マネジャー研修」を通じて、
「マネジメントとは何ですか?」
と質問すると、さまざまな答えが返ってくる。
・部下育成
・組織運営
・組織の仕組み作り
・目標達成の支援
具体的にマネジメントとは何をすることなのか? それは、目標を達成させるため、リソースを効果効率的に配分することである。これがマネジメントの基本だ。単なるマネジメントに「組織」や「部下育成」は含まれない。
セルフマネジメント(自己管理)、タイムマネジメント(時間管理)、リソースマネジメント(資源管理)、プロダクションマネジメント(生産管理)、ヘルスマネジメント(体調管理)……と同じだ。
それぞれ個人でできるし、新入社員にも求められる。ここはとても重要なので繰り返すが、マネジメントは「リソースを効果効率的に配分すること」だ。課長や部長だけの仕事ではない。組織メンバー全員がやるべきことだ、ということを知っておいてほしい。
つまり、こうだ。なぜ出世すると負担が増えると思い込むのか? 本人だけでなく、メンバーも全員がマネジャーの仕事を拡大解釈しているからだ。やらなくてもいい仕事まで背負い込み、自分の本来やるべきことができなくなるから「割に合わない」」と思い込むのである。
若手を育てる余裕がない
(2)若手を育てるのに苦労する
口には出さないが、若手社員の育成が難しいと受け止めているマネジャー候補はとても多い。直属の上司が苦労している姿を見ると、「自分にもできるだろうか」と不安になるのもわかる。それよりも深刻なのは、他者視点よりも自分視点のほうに意識を向けている社員が増えていることだ。
「若い人には活躍してほしいが、自分だって安泰じゃない」
「イチイチかまっている暇はない」
不確実性の高い時代になり、「もう自分の将来は安泰だから、あとは後進に道を譲るだけ」と思っている先輩社員はほぼいない。50代になってから焦ってはいられない。30代のうちに別業界でも活躍できるよう、日々スキルを磨かないと、と考えるのだ。
しかも現代の若者は価値観や働き方に対する意識が多様化している。過去のやり方で期待通りに育つとは限らない。たとえば若手の中には、自分のペースで成長したいと考える者も多い。即戦力として期待されることにプレッシャーを感じるせいだろうか。このような状況で、マネジャーが若手を育成する責任を負うことは、大きな負担となる。
(3)不確実性の高い時代に目標達成できない
これは私の分野である。私は企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントだ。私が最も信頼関係を構築できる相手は、断然経営者だ。「絶対達成してもらいたくない」という経営者など、ほとんどいない。
20年近く現場で支援してきて、肌身に感じているのは、「不確実性の高い時代になった」ということだ。決して難易度が高くなっているとは言わない。しかし、予想外のことが毎年のように起こるため、過去のやり方に執着せず、スピーディに変化していく姿勢が大事だ。
柔軟性のある人材なら問題ないが、これまでのやり方に固執したがる人にとっては負担が大きいだろう。組織メンバーの意識や行動もその都度変化させなければならない。変化耐性の低いメンバーがいるとマネジャーが感じるストレスは大きいだろう。
以上、3つの「本当の理由」について解説した。
出世したくない人への3つの対策
それでは具体的な対策について考えてみよう。
出世したがらない人の言い分が「割に合わない」ということだとしたら、「割に合う」ようにすればいい。そこで出世することで以下3つのリワード(報酬)が増えるようになるなら、どうだろうか。
・経済的リワード(給料や賞与など収入が増える)
・時間的リワード(労働時間が減る。自由な時間が増える)
・精神的リワード(やりがいを覚える。キャリア形成にも役立つスキルが身につく)
このうち、労働時間が減ることは現実的ではないかもしれない。しかし出世しても労働時間が今以上に増えなければ、不満は大きくならないだろう。わかりやすく書けば、ストレスなく成果が出ればいい、ということだ。ストレスが少なければ精神的負担は減る。いっぽう成果が出れば精神的リワード(報酬)は、確実に上がるだろう。当然、経済的リワードも上昇するはずだ。
そのために、私が意識してもらいたい対策は以下の3つ。
(1)マネジャーの定義をハッキリさせる
(2)部下育成の責任範囲を明確にする
(3)若者へしっかり啓蒙する
本人任せにせず、組織全体でこの3つの対策をやれば、マネジャーが「割に合わない」と思うことはないはずだ。
(1)マネジャーの定義をハッキリさせる
前出した通り、マネジメントとはリソースの効果効率的な配分である。企業はまず、マネジャー職の役割を明確にする必要がある。「ヒト・モノ・金・情報・時間」といったリソースを効率的に配分することで目標達成させることがマネジャーの仕事である、ということをハッキリさせる。
メンバーシップ型雇用が馴染んだ日本企業は、マネジャーにいろいろな仕事を押し付けている。責任の範囲が不明確なのが問題だ。たとえば部下というリソースに不足分があるのは、果たしてマネジャーの責任か。本人の責任かもしれないし、採用部門の責任かもしれない。ある企業ではマネジャー職の役割を定義して周知徹底させたことにより、マネジャー以外のメンバーの意識が劇的に変化した。このような例もある。
なんでもかんでもマネジャーの仕事ではない
(2)部下育成の責任範囲を明確にする
マネジャー職は、部下育成も求められる。しかし責任の範囲はどこまであるのか? 子どもの成績に関する責任でたとえてみよう。
・学校の先生と同じぐらい?
・予備校の先生と同じぐらい?
・家庭教師と同じぐらい?
・親と同じぐらい?
私の感覚では、親と同じぐらいの責任だ。マネジャーは、学校の先生や予備校の先生のように「教える技術」を専門に学んでいない。自分自身も目標を持っているマネジャーが大半なのだから、親が子どもの勉強を見ていられないのと同じように、マネジャーも部下に付きっきりで教えることなどできない。
職人仕事ならともかく、そうでなければ自分自身で勉強して成長するのが基本だ。しかも小学生や中学生じゃない。社会人になっているのだから、自分の成長は自分で責任を持つのがあたりまえである。このように、責任範囲をしっかりと明確にしよう。そうすることで、確実にマネジャーの心の負担は軽減される。
(3)若者へしっかり啓蒙する
若者たちに当事者意識を持たせることは、とても重要だ。このような啓蒙は、マネジャーに任せてはいけない。場合によっては外部の専門講師などに頼んで定期的に啓蒙するのだ。
1年に1回や2回の啓蒙では、何も残らない。私どもコンサルタントも、粘り強く啓蒙する。若者たちは、ベテラン社員が信じているよりもずっと素直だ。ベテランのマネジャーたちにも、しっかり啓蒙する。
「子離れ」が必要な親と同じように、マネジャーも「部下離れ」が必要だ。「私がいないと、部下は何もできない」などと思い込まないようにすべきだ。背負い込めば背負い込むほど、次世代のマネジャーのなり手がいなくなるからだ。
粘り強い組織改革からは避けられない
このように、出世したくない社員が増えている背景には、マネジャー職の役割の曖昧さ、若手社員の育成の難しさ、不確実性の高い時代における目標達成のプレッシャーなどがある。
最後にワンポイントアドバイスを伝えておく。
それは、特効薬などないということだ。ベンチャー企業ならともかく、歴史のある組織なら環境要因がとても大きい。組織文化を変えるぐらいの気持ちで、粘り強く啓蒙していくことが重要だ。
著者:横山 信弘