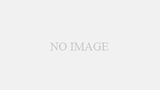東北の太平洋岸を縦断する自然歩道「みちのく潮風トレイル」(青森県八戸市-福島県相馬市)が9日、全線開通5周年を迎える。美しい景色や東日本大震災からの復興を感じられる約1000キロの道程が知られるようになり、国内外のハイカーの注目を集める。(岩沼支局・高橋鉄男)

復興伝え、海外からも注目
トレイルは環境省が復興支援としてルートを設定。4県29市町村の登山道や古道、舗装路面をつなぎ、土地の自然や文化に触れながら歩く。拠点施設の名取トレイルセンター(宮城県名取市)によると、2019年の全線開通から今春までに276人が全線踏破した。
コロナ禍が23年に明けたのを機に、海外メディアでも注目度が高まった。ここ1年で英紙タイムズが「日本で訪れるべき場所14選」に挙げたほか、米紙ニューヨーク・タイムズやウォールストリート・ジャーナルが特集で紹介。海辺の美しさや震災復興を伝える。
センターの運営法人が販売したマップは3月末で約1万2000部。ECサイトで扱う海外向け販売は21年度に21部だったが、22年度は204部、23年度は263部と増えた。最近も欧米やアジアから月20件ほどの注文があるという。
5月に名取のセンター野営場に泊まったオーストラリア人の元外交官バードリー・アームストロングさん(60)は全線踏破中で「景色と出会う人々が素晴らしい。津波で傷ついた悲しい道だが被災建物を残し、忘れないという思いも感じた」と話す。
ただ国内外のハイカーに宿泊先を一括案内するサイトはなく、海外客が宿に電話予約するのは難しい。たき火の規制やごみの扱いなどの啓発も課題だ。
東京電力福島第1原発事故被災地の現状を感じてもらおうと、23年10月には福島県の新地町といわき市の沿岸を結ぶ全長約200キロの「ふくしま浜街道トレイル」が開通。環境省は青森県内で八戸市と十和田湖を結ぶルート作りも進める。全通5周年の記念式典は8日、岩手県宮古市で開かれる。
「休憩所」「荷物配送」「マップ」…受け入れ態勢も着々
みちのく潮風トレイルが全線開通5周年を迎える。国内外から訪れるハイカーに道を快適に歩いてもらい、将来の地域活性化につなげようと住民たちが受け入れ態勢を整備している。
風光明媚(めいび)で陸の秘境とも言われる岩手県山田町の船越半島。2022年7月、休憩所「きのこのいえ」が誕生した。無人で電気はないが、畳の小上がりやトイレを無料で利用でき、そばに沢水もある。
設けたのは地元の佐々木麗子さん(71)。山田町で生まれ育ち、ウオーキングの趣味が高じてトレイルを全線踏破している。
船越半島のルートは霞露(かろ)ケ岳(514メートル)への登頂など1周約35キロで、1日で回りきれず、宿もない「難所」。半島巡りを飛ばしてしまうハイカーもいた。
佐々木さんは半島の魅力を知ってほしいと、知人に頼み、震災後使われていなかったシイタケ乾燥小屋をハイカー用に整えた。利用者記帳ノートには「ここで泊まれて楽になる」「快適に過ごせた」と感謝の言葉がつづられている。
「仲間と掃除したり、ハイカーを見つけたら一緒に歩いたり。私がふれあいを楽しんでいる」と佐々木さんに笑顔が広がる。
久慈広域観光協議会(岩手県久慈市)の事務局長、貫牛(かんぎゅう)利一さん(62)は、海外客向け旅行会社と連携して荷物配送付き宿泊プランを作り、3月から個人事業主として軽貨物運送サービスを本格始動した。
青森県八戸市-岩手県宮古市間の宿から宿へ、ハイカーの荷物を軽ワゴンでパート2人と即日運ぶ。荷物の多い海外客が身軽になれるとあって4~10月は海外から200人超の予約が入り、既に61人が利用した。主な滞在日数の5泊6日で1000泊分の経済効果がある計算だ。
「来てと宣伝するのは簡単だが、受け入れ態勢は誰かが動かないと良くならない。地域が潤えば後に続く」と貫牛さんは語る。
沿線自治体も宮城県気仙沼市などが地元マップを作ったり、岩手県普代村がハイカーに「手を振ろう」運動を展開したりしているが、取り組みには濃淡もある。昨年6月には沿線4県29市町村が環境整備を図る関係自治体協議会を発足させた。
道の管理などを担う宮城県名取市の認定NPO法人みちのくトレイルクラブの代表理事で青森大教授の佐々木豊志さん(67)は「ハイカーや住民、自治体の取り組みがつながって一本の道になる。欧米のように数十年かけ、みんなで育てていけばいい」と話す。

[メ モ] 認定NPO法人みちのくトレイルクラブは、ハイカーを支える施設や団体を「サポーターズ」としてホームページに掲載する。5月末時点で91の団体・施設が登録。ルートまで送迎する宿泊施設のほか、トイレや給水、充電が可能な場所がある。他にも「トレイルエンジェル」と呼ばれるボランティアが各地に生まれている。