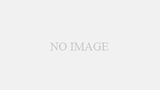円安の影響でますます活性化するインバウンド消費。コロナ前の2019年には訪日者数約960万人、消費額約1兆7700億円と全体の3割以上を占め、「インバウンドの主役」と言われた中国人訪日旅行者の再来に大きな期待が寄せられている。 【画像】インバウンド取り込みはSNSと中国語が必須、個別の体験と特別感がカギに 一方で、処理水放出の影響や「爆買い」離れなど、その動向にも注目が集まっている。コロナ禍を経て回復しつつある中国人訪日旅行者の最新の現状と、彼らを呼び寄せるためのポイントについて、日本政府観光局(JNTO)の北京事務所長、茶谷晋太郎氏に話を聞いた。 ──中国からのインバウンド傾向について、現状を教えてください。 2022年12月のゼロコロナ政策撤廃を受け、徐々に入国者数は増えています。ただ、アメリカや東南アジアからの旅行者がコロナ前の水準を上回るほど回復しているのに対し、中国からの旅行者はコロナ禍前の3割から4割の水準ですから充分に回復しているとは言えません。処理水の放出問題の影響も一部ではあるようです。 ──処理水放出が、中国人旅行者にどのような影響を与えていますか? 8月末の処理水放出直後は中国社会全体が過剰とも思えるほどに反応したところがあり、団体旅行者については少なからずキャンセルが出たと聞いています。旅行会社も「日本旅行をしましょう」と積極的に売り出せないですし、個人旅行者であっても「今から日本に行くよ」と大っぴらには言えない雰囲気が漂っていました。 ですが、10月の大型連休である国慶節(建国記念日のようなもの)を見たところ、個人旅行客にはほとんど影響がありませんし、2回目、3回目の処理水放出の後も特に反応はありません。個人的には、処理水の影響というのは収束に向かいつつあると見ています。 ──日本の食材を楽しみにされている方も多いと思いますが、影響はありますか。 最近はその危機感も和らいだのかなと感じています。日本に行った人はSNS上で「日本に行って海鮮料理を食べたよ」といった投稿をよくしますが、10月に入ってからぱらぱらと中国人の友人が日本で海鮮食品を食べている写真をアップしているのを見ました。一般消費者の間では処理水と食への懸念は落ち着いてきているのかなと思います。 東日本大震災による原発問題の農作物への影響についても、普通の消費者は問題にしていないと思います。一部のSNSで、日本の食品に対して「汚染されたものだ」と言うような動画が出てくることはありますが、それが一般に広がっているかというと、まったくそうではありません。
コロナ禍による変化はあったのか?
──コロナ禍の前後で、中国からの旅行者に変化はありましたか? 明確な変化があったとは思っていません。「中国といえば団体旅行」というイメージが強いですが、コロナ禍前でも団体旅行は3割に過ぎず、7割が個人旅行でした。コロナ禍以前から、個人がオンラインで航空券やホテルの予約をし、行きたいところに自分たちで行くという個人旅行のスタイルがだいぶ定着していました。 そのなかでも買い物をしに行くというよりは、体験型や滞在型で自分の興味や知的関心に基づいて旅行するというスタイルが定着してきていたので、そういった新たな旅の需要についてもコロナ禍が明けて再び息を吹き返していると感じます。 ──団体から個人、買い物から体験型・滞在型へと変化したきっかけを教えてください。 明確なきっかけがあったわけではなく、中国の方の個人所得がどんどん上がってきたのに伴い、旅のスタイルが洗練されてきているということです。経済的に豊かになってきて、どんな情報もインターネットで得られるようになったことが影響しています。「爆買い」に象徴されるような「モノ消費」から、経験とか体験といった「コト消費」を重視するようになってきました。 また、中国の方は日本とはくらべものにならない厳しい競争社会のなかで生きてらっしゃいますので、そういった日常から解放されるために、癒しや非日常、家族との時間を旅の目的として求めはじめたのかなという印象を持っています。 ──旅行や越境ECを通じて日本製品や食品を購入される中国の方たちが、日本に求めていることは何でしょうか? 中国国内にも日本料理屋がたくさんありますし、中国にいながらにして越境ECを使って日本製品などは買えます。日本の製品や食品に対する信頼があるのは事実です。しかしそういった「日本にいるような体験」はできても、訪日しなければおもてなしを受けながら商品を選ぶというような「日本ならではの体験」はできません。 店員から接客を受けながらものを選ぶというような体験はその場でしかできないですし、円安の影響もあり中国にある日本製品や日本食よりずっと安いですから。